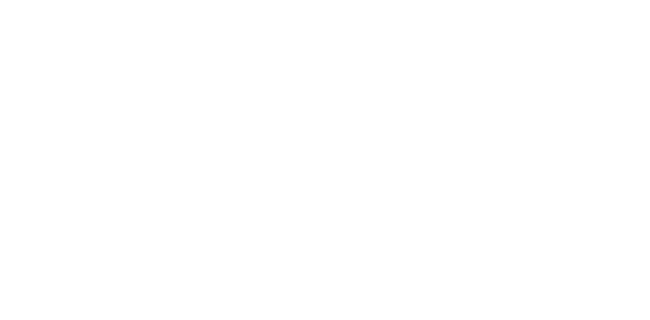平安時代中期の古い話である。時の帝が、「京の三条に住む宗近(むねちか)という刀鍛冶に太刀を打たせよ」と勅命を出した。大役を仰せつかった宗近だが、どうしても満足のいく太刀が打てなかった。困り果てた宗近は、氏神として信仰していた伏見の稲荷(いなり)明神に、足を運んだ。 その途中、宗近は、気高い雰囲気をもった不思議な童子に出会った。童子は、「あなたの悩みはすべてわかっています。私が力を貸しましょう。次に帝の太刀を打つときには、私が相槌を務めます」そう言って雲に飛び乗り去っていった。それは、狐を使者とする稲荷の氏神の化身だった。それから数日後、身を清め、注連縄(しめなわ)を張って鍛冶を始めると、約束のとおり、あの童子がどこからともなく現れて、見事なさばきで相槌を振るった。
「相槌」とは、親槌と呼ばれる刀匠を補佐し、相対して槌を振り下ろすこと。補佐とはいっても、相当な技術を必要とされる。こうしてできあがった太刀は見事な出来栄えで、これなら胸を張って帝に献上できる名刀だった。茎の表には「小鍛冶宗近」、裏には「小狐」の銘が切られた。宗近は稲荷明神に感謝しながら、謹んで「小狐丸(こぎつねまる)」と名付けたという。